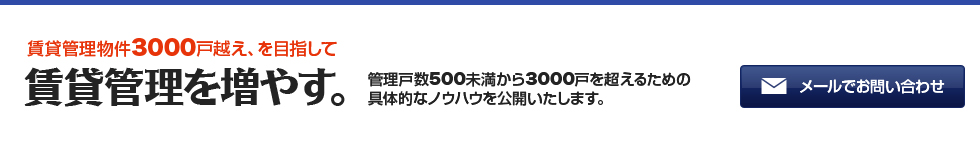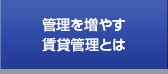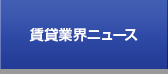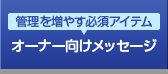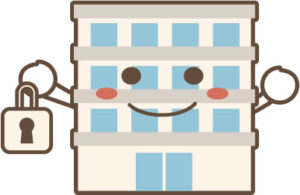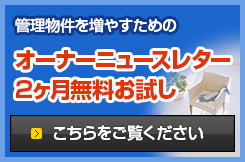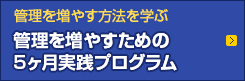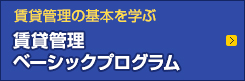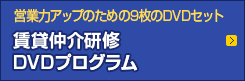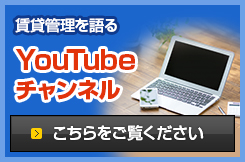賃貸管理中級編も最後になりました。
今回は「鍵の管理」と「大規模修繕工事」について解説いたします。
現在でも、
多くの管理会社が管理物件の鍵を預かっていますが、
他人(ひと)が暮らす住戸の鍵を預かることのリスクを知り、
そのための対策を万全にしておく必要があります。
もし仮に、以下のような事件が起きたら、
管理会社の責任はどうなるでしょうか?
【ケース1】
管理会社の事務所から、管理している数棟のマンションの鍵が盗まれました。
その晩のうちに、その中のマンションの3部屋が侵入盗の被害に遭いました。
管理会社の責任は問われるでしょうか?
【ケース2】
管理している物件で侵入盗事件が発生しました。
防犯カメラから犯人を割り出したところ、
管理会社を半年前に退職していた元スタッフでした。
管理会社の責任は問われるでしょうか?
この2つは、
法的な問題とモラルの問題に分けて検討しなければなりませんが、
おそらく両方ともに管理会社の管理責任が問われると思います。
では、もうひとつの質問です。
わが社では上のような事態が絶対に起こらないと言える、
鍵の管理体制がとられているでしょうか?
もし、預かっている管理物件の鍵の一つ一つに、
物件名称と部屋番号が特定できる情報が表示されていたら、
そしてその鍵が「普通の」金庫に保管されていたら、
ケース1のような事件は防げないでしょう。
鍵を手にした犯人は、そのまま物件に直行するはずです。
もし、預かっている管理物件の鍵を、
社内スタッフの全員が自由に取り出せるような管理状態なら、
ケース2のような事件は防げないでしょう。
最初から犯罪に手を染める気がなくても、
いつでも鍵が取り出せるという環境にいたら
「魔が差す」ということもあり得ます。
実際に、管理戸数と社員数の多い有名な管理会社において、
過去にケース2のような事件が起きています。
表沙汰になっていないケースや、
見つかっていないケースが数多くあったとしても不思議ではありません。
では、どのようすにれば、これらのリスクに対応できるのでしょうか。
ケース1については、
預かっている鍵に物件名と号室が特定できる情報を記載しないことです。
たとえば物件名は物件番号に置き換えれば外部の者には分かりません。
号室は特別なルールを決めておけば外部の者には分からない数値にできます。
たとえば、すべての号室に「ある数字」を足しておくとか、です。
万一、外部の者に盗まれても物件が特定できなければ、
すぐに被害に遭うことはないでしょう。
その間に、盗まれた物件のシリンダーを交換すれば良いのです。
それにしても、その費用負担は大きなものになりますね。
そして、簡単に盗まれないような厳重な管理をします。
これは金庫の性能に寄るところが大きいと思います。
今後も Iot(アイオーティー)を活用した
スマートロックが増えると思いますので、
そのときには、それに合わせた管理体制が必要になります。
ケース2については、
社内にある管理物件の鍵にアクセスできる人を特定する、
という方法があります。
会社の中の数人しか鍵が取り出せない、という管理体制です。
誰でもいつでも取り出せる、というのが業務の上では便利なのですが、
それがリスクをもたらします。
ある程度のアクセス権を設けるのは仕方がないのではないでしょうか。
原状回復の工事中や募集中は
多くのスタッフが自由に使えないと不便、
という事情がありますが、
新しい借主が生まれたら鍵を変えるルールを徹底すれば
問題は解決しますよね。
もうひとつ、
そもそも鍵は預からない、という選択肢もあります。
鍵は新しく入居するときにシリンダーを取り替えますので、
借主には、入居前チェック以外は誰も使用していない新しい鍵が渡されます。
この鍵が3本あるなら3本とも借主に渡してしまいます。
そして自己責任で管理していただきます。
鍵を室内に忘れて「中に入れない」という事態のときは、
24時間営業している鍵屋さんに開けてもらうことになります。
しかし、この方法は、まだ多くの管理会社に普及していないようです。
消防点検のようなケースで、
借主了解の元で室内に入らせてもらう、という時には不便だ、
という意見が多いようです。
いずれにしても、
人が暮らしている部屋の鍵を預かるのは重大な責任があります。
そのことを理解した上で、鍵の管理ルールを決めて、
しっかりと全員で守れるようにしましょう。
内見に使用したり、リフォーム業者さんに渡す鍵は、
以前の借主が使っていた鍵になります。
この鍵の管理は、それほど気を遣わなくても大丈夫です。
事務所の壁に「募集物件一覧」としてかかっていたり、
現場でキーボックスの中に入れられているような使い方で問題はありません。
賃貸借契約が締結されたあとはシリンダーを交換しますので、
その後の新しい鍵は、借主に渡されるまで大事に保管をしておきます。
ここで複製が作られるような隙はつくらないように注意します。
入居時にシリンダーを取り替える費用は、
借主が負担することが慣習として定着しました。
貸主の賃貸借契約上の義務として、
借主に「安全な住居を提供する義務」があるとするならば、
交換費用は貸主が負担すべきだと思いますが、
借主から不満が出ていないのでこのままで良いのだと思います。
ただし、借主が費用を負担したからといって、
シリンダーと鍵の所有権は貸主にあります。
これは、「借主は交換費用を負担しただけ」という解釈で、
ドアに取り付けられているシリンダーと、
それと対をなす鍵は貸主の所有物となります。
なので、退去の時は、すべての鍵を返却してもらいます。
次は大規模修繕工事について解説いたします。
分譲マンションには必ず「長期修繕計画」が策定されています。
修繕工事にかかる総費用を必要な期間で割って、
区分所有者が毎月の修繕積立金として準備しているのが一般的です。
集合住宅になぜ修繕計画が必要かというと、
建物および各設備の耐用年数は概ね決まっていますので、
将来に必要になる費用をあらかじめ知っておくことで、
積み立てなどの準備ができるからです。
賃貸物件も同じで、規模によって工事内容の違いはありますが、
修繕計画と、そのための準備が必要です。
ただ、分譲マンションのように
「長期修繕計画」が策定されていることは少なく、
準備としての積立金も用意されていない大家さんが多いと思われます。
この事実は、賃貸管理にとってとても重要な問題です。
建物や設備は定期的な大規模修繕を怠ると、
老朽化を早めて資産価値を下げてしまいます。
老朽化したまま放っておけば入居促進を妨げて賃貸経営を圧迫します。
また老朽化した建物設備は人に危害や損害を与える可能性があり、
それが損害賠償のリスクを生みます。
何も手を打たないということは大家さんにとって大きなリスクなのです。
それを伝えない管理会社にも責任はあると思います。
(管理委託契約の内容によりますが)
大規模修繕の代表的な工事の内容は、
まず外壁の修繕と塗装・防水工事です。
外壁の修繕工事を怠ったためにタイルが落下して、
通行人や入居者が怪我をしたら大変な事態になります。
そして、バルコニーの塗装と防水工事。
この2つの工事は足場を組む必要があり、それが工事金額を高くします。
屋上の防水工事は、
放っておくと雨漏りで傷んだ箇所から漏水事故をもたらします。
このような事故は、余分な修繕費用の負担を招くだけでなく、
大家さんの損害賠償責任になる可能性もあります。
その他にも、
共用廊下の修繕や鉄部の塗装、経年劣化した設備の交換などが
主な工事内容になります。
特に足場が必要になる工事は大家さんの費用負担が大きくなるだけでなく、
入居者の生活にも影響しますので、
外壁補修、塗装、タイル補修、目地防水、屋上防水などを
まとめて行うことが推奨されています。
大規模修繕工事が必要な時期は12~15年ごと、と言われます。
工事が必要かどうかも含めて、
建物診断を専門家に依頼するところから始まります。
原状回復工事や各部屋のバリューアップ工事と比較しても
費用が高額になりますので、
計画的に資金を確保しておく必要があります。
ある日 突然に提案するのではなく、
大規模修繕工事のための準備や積み立てを、
管理会社から提案できるようにすると、
あなたの賃貸管理の質が上がるのではないでしょうか。
これで全9回の「賃貸管理中級編」を終わります。