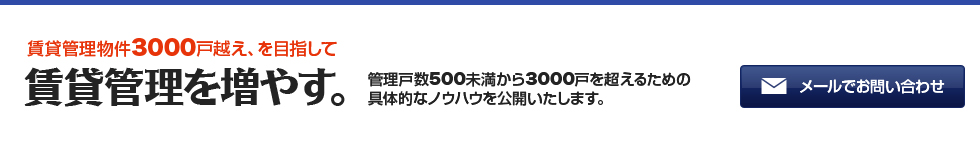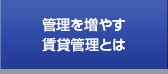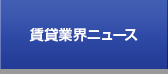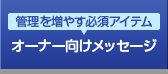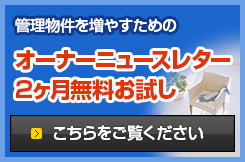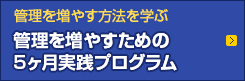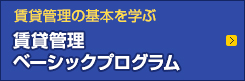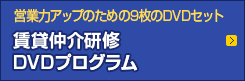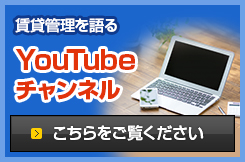管理会社のスキルにとって最も重要な空室対策、
全5回の最終回です。
インターネットで物件の魅力を伝えるために、
一番効果が高いのは写真です。
お客様の視覚に訴えることが出来るのは写真しかありません。
もし、同じ価値の物件が同時期に募集していたら、
その反響の差を付けるのは写真の出来映えです。
今回のビデオでは、
素人でもできる質の高い物件紹介写真の撮り方について解説いたします。
カメラの選び方
物件写真を撮るデジタルカメラにも、
一眼レフ、コンパクトカメラ、スマホなど、
いくつもの選択肢があります。
高価であるほど画質の良い写真を撮ることは出来ますが、
物件写真用カメラの評価は画質だけでなく、携帯性や利便性も大事な要素です。
どのタイプのカメラが良いか、というよりも
次の条件を満たすかどうかで判断してみてください。
まず、一枚の写真に多くの情報を撮り込むことができるか、を検討します。
この場合、一眼レフはレンズ交換が可能なので、
室内を撮るのに適切なレンズを選ぶことができるのがメリットです。
一方のコンパクトカメラには、
24mmの広角レンズを搭載したタイプもありますので、
こちらも狭いところでの撮影には対応しています。
スマホにも、
取り付け可能な広角レンズがあることはありますが、
画質という点で他のカメラにリードを許しています。
窮屈な室内で、なるべく多くの情報を撮り込める性能が必要になります。
つぎに明るい写真が撮れるカメラを選ぶ必要があります。
室内は屋外と比べると想像以上に光が不足しています。
特に日当たりの条件が悪い暗めの部屋は、
カメラにとっては過酷な環境といえます。
「暗い部屋は暗く撮れても仕方がない」と言っては反響につながりませんので、
なるべく明るく撮れる性能が欲しいところです。
一眼レフは、
「シャッタースピード」と「絞り値」と「ISO感度」で対応することができます。
あとで、その機能を活用した撮り方の説明をしますが、
暗い部屋でも明るく撮ることが可能です。
コンパクトカメラは一眼レフほどの対応力はありませんが、
撮影モードとISO感度を選ぶことで明るく撮ることはできます。
しかし1~3万円くらいの廉価モデルでは画質が落ちることもあります。
スマホの最新モデルは、かなり明るく撮れるようにはなっています。
明るさの調整機能もありますが、こちらも他のカメラに一歩譲るという感があります。
物件紹介写真はポスターや風景を撮るのとは違い、
携帯性と利便性も重視されます。
これは、圧倒的にスマホが有利になります。
急に物件写真を撮ることになっても、いつも携帯しているので便利です。
コンパクトカメラも小さく軽く、扱いも簡単ですので、
こちらも携帯性も利便性も合格です。
一眼レフは重く大きく、レンズ交換も手間がかかってしまいます。
物件写真を撮るのに一番適しているカメラを、
あえてひとつ選ぶなら、
コンパクトカメラの高価なモデル、ということになるでしょうか。
スマホも、それなりに使えるようにはなりましたが、
スタッフ個々のスマホを使用することを前提とすると、
その性能に差があることが大きなデメリットです。
————————————-
空室対策に強くなる動画シリーズ⑤がご覧いただけます。
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=awlpmc
では、ここからは撮影するときの注意点について解説を進めていきます。
1. 一枚の写真に多くの情報を撮り込むこと
ポータルサイトに掲載できる写真の枚数には限度があります。
たとえば限度が20枚だとしたら、
外観に1枚、周辺写真に6枚を費やすと、残りは13枚です。
わずか13枚の写真で、すべての部屋と収納と水回り設備とその他の設備、
さらに共用部分、エントランスなどを、お客様に伝える必要があります。
そのためには、一枚の写真の中に、出来るだけ多くの、
「伝えたい情報」を撮り込むのです。
たとえば洋室の写真を撮影するとしましょう。
ベランダ側にカメラを向けて撮るか、
洋室の入り口とクローゼット側にカメラを向けて撮るか、
もし洋室で一枚しか使えないなら、
どちらに見せたい情報が多くあるのかで決める必要があります。
ベランダ側を撮れば、日当たり具合いや、エアコンを写し込むことができます。
入り口とクローゼット側を撮れば、
クローゼットの中や、入り口の先にある廊下や他の部屋を写し込むことができます。
本当は両方を掲載できれば良いのですが、枚数に限りがありますので、
撮影した後に、どちらかを選ぶことになります。
洋室の入り口とクローゼット側にカメラを向けて撮るときは、
入り口のドアを閉めないで、ドアの向こうの風景も一緒に撮り込むように工夫します。
もし、隣がキッチンなら、キッチンセットもフレームに入るかもしれません。
ドアの向こうが通路なら、その先にもうひとつの部屋がある・・・・など、
間取り図を見ながらお客様に想像していただくことができます。
クローゼットも、扉を開けて中の収納スペースが確認できるようにします。
照明器具が付いているなら、それもフレームに入れます。
一枚の写真に多くの情報を・・・・・と言うのは、そういう意味です。
ドアホンのパネルの上にエアコンがあるなら、一緒に撮ってください。
ユニットバスに乾燥機が付いているなら、写り込む角度で撮ってください。
ファインダーを覗きながら、
なるべく多くの情報が入るようなカメラ位置を探してください。
2.明るくピントの合った写真を撮ること。
明るさについては、先にコメントしましたが、
明るさとピントには密接な関係があります。
たとえば人物などを撮るときは、その被写体にピントを合わせるのは当然です。
しかし室内を撮りたい時は、一カ所にピントを合わせるのでは無く、
部屋全体にしっかりとピントを合わせて撮りたいのです。
人物を撮るような、ピントの合う範囲を狭くして撮影する時は、
レンズの絞りの値(あたい)を小さくします。
F2とかF4という値(あたい)です。
この設定のままで室内を撮ってしまうと、全体にピントのボケた写真になってしまいます。
ならば、絞りの値(あたい)を、F8やF11のように大きくすれば良いのですが、
今度はレンズを通る光の量が少なくなって暗い写真になってしまいます。
それを補って光を多く取りこむために、シャッターの落ちる速度をゆっくりに調整します。
すると次は、手ブレ写真となる可能性が高いです。
そこで暗めの室内を明るくピントを合わせて撮るためには、
絞りの値(あたい)を大きくして、
シャッタースピードを遅くして、
ブレないために三脚を使うのが正しい撮り方になります。
それでも暗いときは ISO感度を上げて調整します。
一眼レフの場合は、これらをひとつひとつ調整して撮ることができますが、
コンパクトカメラの場合は、撮影モードを選ぶことで、
ピントの合う範囲が広い設定を選ぶことができます。
小さなコトですが、明るさとピントを意識して撮ることで、
綺麗な分かりやすく見やすい室内写真を撮ることができます。
3.カメラを構える適正な位置とは
カメラの構え方の基本は、カメラと床を垂直にすることです。
壁や柱とカメラが平行になるように構えます。
こうすることで、柱や壁のラインが真っ直ぐの、見やすい写真を撮ることができます。
もしカメラを上に向けると、柱と壁が「ハの字」になってしまい不自然な写真になります。
反対に下に向けると柱と壁が「逆ハの字」になり、これも不自然です。
あえて一枚だけ、インパクトのある写真にするために、
わざと上に向けたり、下に向けて撮ることはあるかもしれませんが、
基本は常に床と垂直に、壁と平行に構えることを基本としてください。
カメラは床から70~80cmくらいの位置に垂直に構えると、
床と天井のバランスがちょうどよくフレームに収まります。
もし天井の高い部屋の場合は、少し位置を高くするなどの調整をしてみてください。
管理物件のインターネット掲載には、写真の質にこだわってください。
限られた枚数の中で、物件の「売りのポイント」を、
お客様に見ていただきたいポイントを、余すところなく表現できるようにしましょう。
空室対策に強くなる動画シリーズ⑤がご覧いただけます。
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=awlpmc